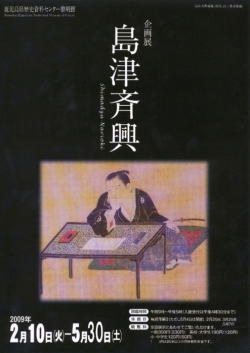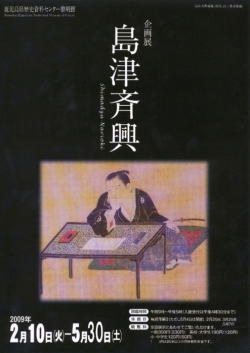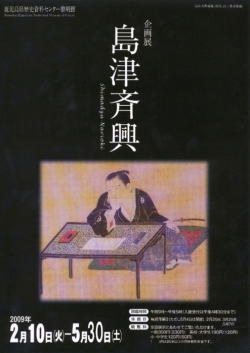 |
| 企画展『島津斉興』チラシ |
第二十二話「島津斉興の密書 −斉興と斉彬と久光の関係−」
2009年5月のゴールデンウィーク、私は久しぶりに鹿児島を訪れたのですが、その際に鹿児島県歴史資料センター「黎明館」において開催されていた企画展『島津斉興』(しまづなりおき)を見学してきました。
企画展では、島津斉興にまつわる貴重な史料が数多く展示され、非常に興味深いものになっていましたが、それら展示品の中でひと際私の目を引いたのが、嘉永4(1851)年1月29日付けで、斉興が息子の島津久光に宛てた密書です。
「大急キ書きちらし申候」で始まる斉興の密書を読んでいると、斉興とその子供達である斉彬と久光という兄弟の関係が大きく浮き彫りにされていくような気がします。
まずは、その密書の内容を紹介する前に、密書を書いた島津斉興のことから話を始めたいと思います。
文政6(1809)年6月17日、島津斉興はわずか18歳の若さで父・島津斉宣(しまづなりのぶ)の跡を受け継ぎ、島津家27代の薩摩藩主に就任しました。
斉興が10代の若さにもかかわらず、急遽藩主に就任したのには大きな理由があります。
「文化朋党事件」、別名を「近思録崩れ」と呼ばれるお家騒動が起こり、藩主の斉宣がその責任を取る形で隠居せざるを得なくなったからです。
斉宣の父、つまり斉興の祖父にあたる島津家25代当主の島津重豪(しまづしげひで)は、鎖国下の日本にあって西洋や中国の文物に興味を持つなど、進取気鋭の精神に満ちた人物でしたが、その反面、豪放磊落な性格に加えて、第11代将軍・徳川家斉の岳父として権勢を誇り、放蕩財政を繰り返したため、藩財政は急激に逼迫しました。
重豪の治世の影響で、薩摩藩は500万両という、とてつもない借財をこしらえることになるのですが、その藩財政の立て直しを図ったのが、重豪の跡を受け継いだ子の斉宣でした。
(付記:1両を5万円と少なく見積もって計算しても、500万両は2500億となる。当時の貨幣価値は現在の数十倍であることを考えると、とてつもない高額である)
斉宣は樺山久言(かばやまひさこと)や秩父季保(ちちぶすえやす)といった硬骨で慧眼ある武士達を抜擢して藩政の中枢に据え、次々に藩政改革に着手しました。重豪の放蕩財政を改めるべく、藩内においては緊縮財政を発動し、藩財政の立て直しを図ったのですが、その急激な藩政の方針転換が隠居である重豪の怒りに触れました。重豪は斉宣の腹心ら13名に対し切腹を命じ、その他数多くの藩士が遠島、謹慎などの処罰を受け、また重豪は藩主である斉宣を強制的に隠居させたのです。
これが「文化朋党事件」(別名「近思録崩れ」、「秩父崩れ」)と呼ばれるもので、この騒動により、斉宣の治世は終わりを告げ、その跡を受け継いだのが斉宣の子の斉興でした。
このように藩主は斉宣から斉興へと代替わりすることになったのですが、わずか18歳の青年であった斉興に実権は無く、実質的な藩政の権力を握ったのは隠居である重豪でした。重豪は斉興の後見人となり、再び藩政を掌握したのです。
この重豪親政は、重豪が亡くなる天保4(1833)年3月までの間、約24年間の長きに渡って続くことになるのです。
こうした飾り物の藩主への就任が、後年斉興が斉彬に跡目を譲るのを渋った間接的な要因となっているのではないかと以前エッセイに書きましたが(薩摩的幕末雑話 第三話「父と子−島津斉興と斉彬−」参照)、斉興が斉彬に跡を譲りたがらなかったもう一つの大きな原因は、斉彬が重豪を生き写したかの如く、同じような趣味・趣向を持つ人物であったからです。
重豪の死後、ようやく藩政の実権を握ることが出来た斉興は、茶坊主上がりの調所広郷(ずしょひろさと)を使い、藩内に大きな財政改革を断行し、借金まみれであった藩の財政状況を立て直し、ようやく薩摩藩の財政も息を吹き返していました。
しかしながら、自らの跡目を継がせるべき世子の斉彬が、重豪と同様に西洋の文物に興味を持ち、蘭学者や洋学者らと盛んに交流を持つなど、斉興から見れば金のかかる派手な活動をする人物であったため、次第に斉興は斉彬を嫌うようになっていったのです。
このように斉興の子の斉彬が、500万両という多額の借財をこしらえる原因となった重豪と「うり二つ」であったことが、斉興をして斉彬に家督を譲ることを躊躇わせる大きな原因となりました。そしてそのことは、その後の二人の関係を決定づける、最大の不幸ともなったのです。
斉興にとって、重豪という存在は一種のトラウマになっていたのではないでしょうか。
前述のとおり、斉興は藩主に就任してからも、非常に長い期間に渡って後見人である重豪の目を気にしながら、藩内の政治を行わなければなりませんでした。父である斉宣が重豪の怒りに触れて強制隠居させられたのは、斉興の記憶の中に鮮明に焼きつけられていたに違いありません。
その結果、斉興は重豪に対して一種のトラウマ的な感情を持つに至ったと私は推測しています。どんな時にあっても重豪の機嫌を伺いながら事を進めなければならなかった斉興の苦労は察するに余りあります。そのことが斉興の重豪アレルギーのようなものを引き起こしたと私は推測するのです。
このように斉興の経験からくる感情を考えると、斉彬が重豪と趣味、趣向、性格が大変似ていたことは、斉興が斉彬を忌み嫌う十分な原因となったことは想像に難くありません。
また、斉興は斉彬が藩主に就任すれば、重豪がそうであったように、藩政にとっては直接重要ではない部分に多額の金を使い、藩が再び昔のような苦しい財政状態に陥るのではないかと危惧しました。そしてその危惧は、いつしか自分の跡目を正室の子である世子・斉彬ではなく、側室の子である庶子・久光に継がしたいと考え始めるきっかけとなったと言えましょう。
久光の実母である斉興の側室・由羅(ゆら)の方は、斉興が最も愛した女性で、斉興は江戸への参勤交代の際にも由羅の方を一緒に連れて行ったほどです。斉興にとって、そんな愛すべき女性の子供である久光が可愛くないはずはありません。
また、久光は斉興好みの保守的で実直、温厚な人柄でしたので、なおさら斉興は久光のことを気に入り、いつしか自らの跡を継がせたいと考えるようになりました。
しかしながら、そんなことは世間一般的には許されないことです。
当時斉彬は三百諸侯中の世子の中でも随一と噂された名高い人物であり、幕閣の老中・阿部正弘や徳川御三家の一つ水戸藩主・徳川斉昭ら諸大名とも親しい交流を持ち、その藩主就任を今か今かと待ちわびられた人物でした。
そんな世間的にも立派な世子である斉彬を差し置いて、側室の子である久光に跡を継がすことは、世間的に言っても、また倫理上からも許されるはずがありません。
そのため、斉興はいつまでも斉彬に跡を継がすことなく、藩主の座に居座り続け、気がつけば、斉彬は齢40代に入ろうとしていました。当時の40歳と言えば、もう壮年を通り越し、老年の域に入ろうかという年代であり、斉彬がその年齢まで世子の座に居たのは一種異様な形であったと言えましょう。
もしかすると、斉興は斉彬が先に亡くなるのを待つために、自分が元気な間はずっと藩主の座に居座り続けようと考えていたのかもしれません。親よりも子が先に亡くなるのを待つこと自体、自然の摂理に反する無理ある考え方でしょうが、斉興の斉彬嫌いを考えると、そんな風に考えていた可能性も否定出来ないと思います。
また、斉興なら斉彬が亡くなれば儲けもの、もし斉彬がその間に何か問題を起こそうものなら、廃嫡ということも視野に入れて考えていたやもしれません。
このように斉興はいつまでも斉彬に家督を譲ろうとはせず、世間的にも薩摩藩は非常にいびつな状態が続いたのですが、斉彬としてもこのまま黙って座しているわけにはいきません。自らの得た知識や経綸を一刻も早く藩政に生かしたいと考えていた斉彬は、自ら藩主の座に就くべく、ある禁じ手を打ちました。
斉彬は薩摩藩が琉球を通じて行っていた密貿易を当時幕閣の中心人物だった老中・阿部正弘にリーク(密告)することにより、斉興の隠居を画策したのです。
当然この密告は、斉彬と斉彬の藩主就任を熱望する阿部が事前に示し合わせて行ったことでした。斉彬は自らの藩の汚点をさらけだすことにより、斉興の隠居を誘発しようと考えたのです。斉彬にとっては、いわゆる諸刃の剣を使ったと言えましょう。
この一件により、斉興の腹心で薩摩藩の財政改革を成し遂げた家老・調所広郷がその責任を一身に負い、服毒自殺して果てることになるのですが、斉興自身はと言うと、隠居する気配もなく、一向に藩主の座から降りようとはしませんでした。
つまり、斉興は居直ったのです。
このことをもってしても、斉興の藩主への執着心は並々ならぬものがあったことがうかがえます。また、それと同時に、この一件で斉興は藩主の座を狙う斉彬に対する憎悪の念をさらに深めたと言えるでしょう。
こういった出来事が積み重なり、後に「お由羅騒動」と言われるお家騒動が起こるなど、斉興と斉彬の関係は悪化する一方でしたが、最終的に斉興は隠居へと追い込まれることになります。それはまさに、斉彬の藩主の座への執念が、斉興のそれに勝った結果であったと言えましょう。
嘉永4(1851)年2月2日、ようやく斉彬は斉興の跡目を継ぎ、島津家28代当主の薩摩藩主に就任することになります。
斉興はそんな斉彬の藩主就任が目前に迫った1月29日、当時国元の薩摩にいた久光に宛てて、江戸から急ぎ密書を書き送りました。
これが最初に紹介した企画展『島津斉興』に展示されていた斉興の密書です。
この密書には、当時の斉興の斉彬観が事細かに書かれており、斉興が斉彬の藩主就任を内心では快く思っておらず、一種の憎悪まで感じさせるものであったことがうかがい知れる内容となっています。
まずは、その密書の内容を見てみましょう。
用書
申入周防とのへ
大急キ書きちらし申候
極密内用申入候、此度代合も相済、表向登城ニ而被仰出も相済候ニ付為心得申入候、
二白、玉里作事出来之上ハ、引移可申心得ニ付、夫迄之内下り不申候間、能々気付可被申候、
一 是迄通り諸事少シも相替無之様、
一 自分とちかいうたくゝりにてさかしいくせ有之候事、
一 勇気少シ世事計ニ而不宜、
一 万事もれやすし、
一 豊後より昔より之家宝定法能々申上候様、
一 無用之物すき多有之、
一 にきやか好之方、
一 少膽ニ有之、
一 付之者人きらい有之、
一 右之外ニも其元心付之程も可有之候間、日夜由断なく心掛、手堅く相勤可被申候、城下其外士共之気ニ合不申やと案申候、無役若者其外共さわき立不申、是迄通手堅万事相勤心掛、無ゑき之事とも不致候様、能々気ヲ付可被申候、心付之侭不取敢申入候、猶此後心付候事も候ハヽ知せ可申候間、密ヽ豊後と談可被置候、以上
(※下線部横に小さな文字で)
又申入候、世上人気引受候所、いかゝニ相成候や、難有かり候や、きらい候や、豊後と被申談極内御知せ頼入候、
正月廿九日認
くれヽも返事ニハ不及候、以上、
大急キ書改けし申候、
此書付豊後へ御見せ候而も不苦候、以上、
(密書の原文は『鹿児島県史料 玉里島津家史料十』より抜粋。なお、企画展『島津斉興』に展示されていた原資料を参考に、筆者が若干の補足等を加えています)
(現代語訳by tsubu)
用書
周防殿(久光のこと)へ申し入れます。
大急ぎで書き散らします。
極内密のことですが、この度代替わり(斉彬の藩主就任を指す)も済み、表向きは登城の上、仰せ出されも済んだので、今後の心得を言っておきます。
二白(追伸のようなもの)、玉里別邸の改修工事が完成した上は、そこに引き移るつもりでおり、それまでの間は薩摩に下ることはないので、よくよく気をつけておいて下さい。
一つ、諸事(藩政その他を指すものと思われる)については、これまで通り少しも変わらないものと考えること。
一つ、(斉彬は)自分とは違って疑り深く、小賢しい性格である。
一つ、(斉彬は)勇気が少なく、世事の取り扱いも宜しくない。
一つ、(斉彬は)何事においても情報が漏れやすい。
一つ、豊後(城代家老・島津豊後。斉興の腹心)から昔より代々家に伝わる定法を言って聞かせているようだが……。
一つ、(斉彬は)役に立たない物を好むことが多い。
一つ、(斉彬は)騒ぎを好む方である。
一つ、(斉彬は)肝っ玉が小さいところがある。
一つ、(斉彬は)付きの者の好き嫌いがある。
一つ、これらの他にもそなたが気づいていることもあると思うが、日夜油断することなく心掛け、手堅く勤めるように。
また、城下やその他の者共の人気に合っていないのではないかと案じており、無役の若者やその他の者共が騒ぎ立てぬよう、これまでの通り何事も手堅く勤めるよう心掛け、無益なことを致さぬよう、よくよく気をつけて下さい。
(また、世上の人気(斉彬の人気のことを指すものと思われる)についてはいかがですか? やはり難があるという感じですか? 嫌われている感じですか? 豊後と相談の上、極内密に知らせて下さい)
取りあえず思いついたことをそのまま書いておきました。なお、今後気づいたことがあれば知らせるよう、密かに豊後と相談しておいて下さい。以上。
正月二十九日に認める。
以上、くれぐれも返事には及びません。
大急ぎで書いたものですが、この書付については、豊後に見せても構いません。以上。
この密書は、斉彬の藩主就任が目前に迫った嘉永4(1851)年1月29日(斉彬の藩主就任は2月2日)、斉興が国元の薩摩にいる久光に対して急いで書き送ったものです。
『鹿児島県史料 玉里島津家史料十』所載の芳即正氏による解題によると、毎月29日は、江戸薩摩藩邸から国元・薩摩へ定期便が出る日となっていました。斉興はその便に間に合わせるため、一気に急いで書いたのでしょう、私が見た原物の書簡は、まさに斉興曰く「書き散らす」ような筆致で書かれています。
また、文面中に「極密」という言葉が使われていたり、最後に「返事には及ばない」と書かれていることから、これが極秘文書として久光に送られたことがよく分かります。
密書の中身を読んでいくと、非常に衝撃的なことが書き連ねられています。
特に注目するべき点は、斉興の斉彬観が事細かく書かれていることです。当時の斉興の正直な心情を吐露しているような内容です。
斉興は密書の中で、斉彬の性格を「疑り深く、小賢しい」、「勇気が少ない」、「肝っ玉が小さい」などと、罵倒にも近い言葉で表現しています。その文面からは、いかに斉興が斉彬を買っていなかったか、つまり嫌っていたのかがよく分かるのではないでしょうか。
また、斉興は斉彬のことを「無用之物すき多有之(役に立たない物を好むことが多い)」、「にきやか好之方(騒ぎを好む)」と表現している部分は、斉彬と重豪の趣向がよく似ていたことを暗に示唆しているような気がします。
斉興曰く「無用之物」とは、重豪や斉彬が好んだ西洋や中国の文物やそれにまつわる事業を指すものであり、また、「にきやか好之方」とは、要らぬ政治話などに首を突っ込みたがる性格を表現しているのではないかと思われます。
斉興が斉彬に重豪の影を色濃く見たのは、こういった部分からであったことが、この密書からも窺い知れるのではないでしょうか。
それでは、なぜ斉興は斉彬の藩主就任を目前に控えたこの時期に、慌ただしく久光に対してこのような密書を書き送る必要があったのでしょうか。
密書の中身を読んでいくと、斉興が斉彬の悪口とも言える文言を次々と並べ立てて書いている箇所にどうしても目を奪われがちになってしまいますが、大事な箇所はやはり後半部分、斉興が藩内の様子を詳細に知りたいと希望しているところだと思います。
わざわざ斉彬の悪口を書くためだけに、定期便の出発に間に合わせるべく、急ぎ密書を書き送る必要性はないと思います。
つまり、この密書が慌てて書き送られた一番の主目的は、斉興が自らの隠居後の藩内の様子を詳細に知りたいがためであったのではないでしょうか。
例えば、密書内の「城下其外士共之気ニ合不申やと案申候、無役若者其外共さわき立不申」や「世上人気引受候所、いかゝニ相成候や、難有かり候や、きらい候や」という部分からは、斉興が自らの隠居後の藩内の動静を非常に気にしていたことが窺えます。
「騒ぎが起こっていないだろうか?」
「斉彬の人気はどうなのだろうか?」
と、斉興が心配している辺り、もしかすると、万が一斉彬の藩主就任により藩内が動揺するようなことがあれば、斉興は何らかの別の巻き返し策を考えていたやもしれません。
斉興は隠居せざるを得なくなったとは言え、まだまだ藩政を執ることに大きな未練が残っていたものと思われます。
また、密書の最初に「玉里作事出来之上ハ、引移可申心得ニ付(玉里別邸の改修工事が完成した上は、そこに引き移るつもりでおり)」と書いていることは非常に重要な点です。
玉里別邸とは、斉興が鹿児島城下の郊外に造営した屋敷のことで(現在の鹿児島女子高等学校の敷地内に茶室と黒門のみが現存)、隠居後はここに引き移るつもりと書いているということは、斉興がいずれ江戸から薩摩に帰国しようと考えていたということです。
隠居した大名は江戸住まいが通例であったのにもかかわらず、斉興が薩摩への帰国を考えていたということは、何らかの形で藩政に対しての影響を保とうと考えていたことが推察されます。(この斉興帰国の一件は、後に斉彬が阻止することになります)
このように、斉興が自らの心許した相手である息子の久光と腹心の島津豊後に密書を急遽出すに至ったのは、斉彬の藩主就任後の藩内の状況や動静を探り、何らかの次の一手を打つためであったと私は推測しています。
また、斉興が殊更大げさに斉彬の悪口を密書内に書き連ねたのは、斉彬に対する恨みつらみがそうさせたと考えられる他、斉彬の藩主就任が斉興の意志ではなかったことを久光に印象付ける目的もあったのではないでしょうか。
斉興が斉彬ではなく、久光に跡目を譲りたいと考えていたことは前述したとおりですが、斉興としては藩主にすることが出来なかった久光の心を慰撫する目的も、この密書の中にあったように思われます。久光に対して「手堅く相勤め」と指示していることを見れば、「斉彬が藩主に就任してしまったが、そのことにより腐らずに、これまで通りしっかりと勤めあげよ」という、斉興のメッセージが込められているような気がします。
また、誠にうがった見方かもしれませんが、私は斉興が久光に対し、「今は我慢してこれまで通りちゃんと勤めておくように、いつかチャンスが巡ってくるやもしれぬから……」という意味を暗に込めているような気がしてなりません。
ただ、密書を受け取った当の久光についてですが、斉興とは違い、斉彬との関係は悪いどころか、非常に良好であったようです。斉彬自身が久光に対して大きな期待を寄せていることを示す史料が現存し、藩政や国事のことに関しても、斉彬は久光によく意見を求め、二人の関係は良好だったと伝えられています。
斉興が久光に期待し、斉彬を嫌う一方で、久光は斉彬のことを師事していたのですから、誠に皮肉な話です。
久光は一体どのような気持ちで、斉興の密書を読んだのでしょうか?
その点は非常に興味がありますが、久光自身も少なからず野心のある人物でしたので、自らの藩主就任が完全に断たれたことを残念に思う気持ちも少しはあったようにも思えます。
これまで斉興の密書が書き送られる経緯や背景について考察してきましたが、最後に一点、斉彬の死のことについて書いて終わりたいと思います。
斉彬の死に関しては、昔より「毒殺説」がささやかれ、鹿児島出身の歴史作家・海音寺潮五郎氏もその著作の中で強くそのことを主張されています。
斉彬が急死したのは、安政5(1858)年7月16日のことで、その8日前、城下の天保山で軍事調練を行っている最中、俄かに体調を崩し発熱したことが原因でした。
斉彬の死因はコレラと言われていますが、発病から死亡までの日数が非常に短いことと、これから書くように、斉彬の死が余りにタイムリーであったことから、現在においても毒殺説は根強く唱えられています。
当時、幕府大老の職にあった井伊直弼は、朝廷に許可を得ないまま無断で諸外国との条約に調印し、その後「安政の大獄」を引き起こすなど、強権を発動することにより、幕府政治の安定と秩序を保とうと考えました。
斉彬は井伊の政治手法は日本の国を滅ぼす危険なものと考え、それに対抗するために、薩摩から兵を率いて京に入り、朝廷より幕政改革の勅許を受け、強大な兵力を背景に、幕府に対し幕政改革を迫るという、非常に大胆な計画を練り上げました。
(付記:斉彬が本当に率兵上京計画を断行するつもりであったかどうかについては、現在でも色々と諸説、議論が分かれているところですが、私は後年久光が「斉彬の意志を引き継ぐ」という形をとり、同じ手法で兵を率いた上京計画を実施しているところから、同計画は斉彬が立案し、実行する心積もりであったものと判断しています)
斉彬が計画した率兵上京計画は、一種のクーデターのようなものです。斉彬は井伊直弼に対抗し、日本の国難を救うためには、最早尋常の手段ではらちが開かないと考え、この率兵上京計画を立案したのですが、一方でその計画は薩摩藩の存在自体を揺るがしかねない、非常に危険な賭けでもありました。
そんな大計画を実行しようと考えていた矢先、斉彬が急死したため、古来斉彬の死に関しては、薩摩藩の危機を危惧した隠居の斉興が、自らの息のかかった配下の者に命じて、斉彬に毒を盛り、暗殺したと言われています。
確かに、斉彬の死後の斉興の動きには、少々きな臭い部分が感じられなくもありません。
斉彬の死後、久光の子の忠義が藩主に就きますが、隠居の斉興がその後見人となり、斉彬が興した集成館事業を廃止するなど、藩政に関して180度の方針転換を行いました。それはまさに斉彬の治世の全否定とも言うべき行動であり、この点から見ても、斉興の斉彬に対する一種の嫌悪が見て取れます。
しかしながら、この斉彬毒殺の一件に関しては、決定的な直接証拠となる史料がないため(今後も出ることはないでしょう)、あくまでも推測の域を出ない話です。
ただ、斉彬の死は余りにもタイムリーであったことと、斉興の斉彬に対する感情を考え併せると、毒殺説に関しては肯定までは出来ないまでも、完全否定は出来ない話だと私は考えています。
最後は推測の域を出ない話ばかりとなってしまいましたが、今回紹介した斉興の密書を読んでいると、斉興の凄まじいばかりの藩主への執着心と斉彬に対する憎悪、そして久光に対する愛情が見て取れるような気がします。
その点から考えると、案外この密書は斉彬毒殺説の傍証の一つになり得るものなのかもしれません。