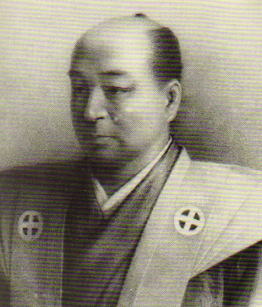 |
| 島津斉彬肖像画(キヨソネ画)鶴嶺神社蔵 |
(西郷隆盛の生涯)西郷誕生から西郷の江戸行きまで
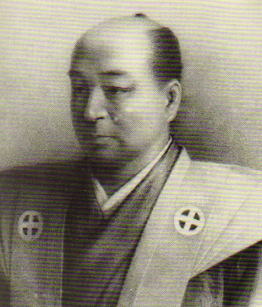 |
| 島津斉彬肖像画(キヨソネ画)鶴嶺神社蔵 |
【西郷誕生】
文政十(一八二七)年十二月七日、西郷隆盛は鹿児島城下の下加冶屋町(したかじやまち)で生まれました。幼名は小吉、長じて隆永、隆盛と名乗り、通称は吉之介、善兵衛、吉兵衛など数多くの名前を使用しましたが、吉之助という名が一般的です。また、南洲(なんしゅう)は雅号です。
西郷家の祖先は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した武将で、南朝の忠臣と言われた菊池武光と伝えられています。後年のことになりますが、西郷が奄美大島に身を隠すことになった際、「菊池源吾」(注)という変名を使用していることからも、西郷家が菊池氏の後裔であったことをうかがい知ることが出来ます。(注:菊池源吾の名に「吾の源(祖)は菊池なり」との意味を込めたと伝えられています)
池田米男『南洲先生新逸話集』によると、西郷家の祖である菊池氏が姓を西郷と改めたのは、当時居城としていた増永城が肥後国菊池郡西郷村(注)にあったからのようです。(注:現在の熊本県菊池市七城町砂田西郷。現在、その地に徳富蘇峰が揮ごうした「西郷南洲先生祖先発祥之地」という石碑が建っています)
また、肥後国菊池郡を本拠としていた西郷家が、薩摩藩の島津家に仕えるようになったのは江戸中期・元禄年間のことで、島津家中での西郷家の家格は御小姓与(おこしょうぐみ)に属し、薩摩藩の士分(武士の身分)では、下から二番目の下級藩士でした。
西郷は幼少期から青年期にかけて、とても貧しい生活の中で成長したと伝えられています。西郷自身は四男三女の七人兄妹の長男として生まれ、下には吉二郎、信吾、小兵衛の三人の弟と琴、鷹、安の三人の妹がいる大家族の中で育ちました。
鹿児島出身の歴史作家で西郷研究の第一人者であった海音寺潮五郎(かいおんじちようごろう)は、その著書『西郷隆盛』(朝日新聞社)の中で、西郷が奄美大島で娶った島妻・愛加那(あいかな)の子の菊次郎が語り遺した話として、
「おやじの若い頃はずいぶん貧乏であったようで、食うだけがやっとで夜具ふとんなども不足でごわすので、冬の夜など一枚のふとんを兄弟全部で着てあっちこっちから足を突っこんで寝るわけでごわすが、寒かもんじゃから、夢うつつのうちについ引っぱり合ってしもうて、はっとして眼をさましては、あやまったり、笑ったりじゃったそうでごわす」
という逸話を紹介し、当時の西郷家の貧しい暮らしぶりが描かれています。
【郡方勤務】
西郷が十六歳の時、藩の郡方書役助(こおりかたかきやくたすけ)に任命されます。
郡方書役助とは、現代で言うところの農政事務所の事務官といった役職ですが、「助」という言葉が物語っているように、それは補助、つまりアルバイトのような役職でした。
他藩に比べて武士の人口比率が高かった薩摩藩(注)では、武家の子弟がある程度の年齢に達すると、各自家計の助けとなるように低い役職に付ける慣習がありました。例えば、書の巧みな者は書役(事務官)、武術の長けた者は藩校演武館の助教(教員)といったように、個人の資質や能力に応じて様々な役職に就かせたのです。(注:薩摩藩では約四人に一人が武士であったと言われています)
西郷は幼少期に負った右腕のケガのため、武芸を諦めて学問に精を出していたことから、同世代の中でも読み書きや算盤に秀でていたのでしょう。西郷はその能力を買われて、事務職に任命されたものと思われます。
また、西郷が勤めた郡方は、藩内各地に出張することも多く、体力のいる役職でもありました。西郷の生まれついての雄大な体格も、郡方の事務官に任命された理由の一つだったのかもしれません。
西郷が郡方書役助に任命された時の郡奉行は、迫田太次右衛門という人物でした。
迫田は鹿児島城下でも聞こえた気骨ある人物で、西郷は迫田に大きな影響を受けたと伝えられています。
迫田については、次のような逸話が残されています。
ある日のこと、地方を巡視していた迫田のもとに藩庁から通知書が届きました。迫田が内容を確認すると、そこには「多少風水害の被害があったとしても、今年の年貢の減額は認めないように」と書かれていました。
迫田はその通知書を見るなり、地方巡視を途中で中止して鹿児島城下に帰り、役所の門に次のような一首を書き残しました。
「虫よ 虫よ 五(いつ)ふし草の根を断つな 断たばおのれも 共に枯れなん」
虫とは「役人」のことを意味し、五ふし草とは「農民」のことを指しています。
迫田は、「役人が農民に対して過酷な課税を強いることは、自らを破滅に導くことに等しい」と、重税に苦しむ農民たちの窮状を憤り、藩の苛斂誅求な年貢の取り立てを暗に批判したのです。
西郷はこの迫田から農政に関することを一から学びました。西郷が藩内の農政事情に精通し、後に農政に関する建言書を書いて提出するまでにいたったのも、この迫田の影響を強く受けたものだと伝えられています。
また、郡方勤務時代の西郷には、次のような逸話も残されています。
ある日のこと、ある農家の主人が租税の支払いが出来ず、飼っていた牛を売却して税の支払いに代えようとし、夜陰ひそかに牛と別れを惜しんでいました。西郷はその姿を目撃し、その農民の窮状を憐れみ、納税額を減額するよう役所に掛け合ったのです。
また、西郷はその他にも、時には重税に喘ぐ農民たちの窮状を黙視できず、自らの手当てを恵むこともあったと伝えられています。
このような西郷の愛情深い性格は、郡方勤務時代に培われたものだと言えます。そしてまた、後年西郷が到達する「敬天愛人(けいてんあいじん)」の思想は、郡方での経験がその源流にあるとも言えるのです。
【お由羅騒動】
西郷が郡方に勤務して五年後の嘉永二(一八四九)年、薩摩藩に大きなお家騒動が起こりました。
俗に言う「お由羅騒動(おゆらそうどう)」と呼ばれているものです。
島津家二十七代当主で、薩摩藩第十代藩主であった島津斉興(しまづなりおき)は、当時既に五十八歳と高齢であったにもかかわらず、なかなか隠居しようとはしませんでした。斉興の正室周子(かねこ)が産んだ世子(藩主の世継ぎ)の斉彬は、既に四十歳になり、老齢の域に入っていましたが、斉興は一向に家督を斉彬に譲ろうとはしなかったのです。
(付記:斉興と斉彬の二人の関係については、薩摩的幕末雑話:第三話「父と子−島津斉興と斉彬−」または第二十二話「島津斉興の密書−斉興と斉彬と久光の関係−」を併せてご覧下さい)
当時の社会通念から考えると、この状況は異例だったと言えます。当時は世子が二十代にもなれば、藩主は自ら進んで隠居し、子供に家督を譲るのが通例であったからです。
斉彬は幼少時代から聡明と謳われ、将来を嘱望された人物であり、進取気鋭の性格で、当時の日本を取り巻く諸外国の事情にも通じ、諸大名の間でも名高い人物でした。
しかし、実父の斉興は、まるで斉彬のことを忌み嫌うかのように、いつまで経っても隠居しようとはしなかったのです。
このような異常な状態が続くと、藩内には悪い風潮が生じ、様々な憶測を呼ぶものです。斉彬が藩主の資格を十分に兼ね備えながらも、いつまで経っても家督を継ぐことが出来ないのは、斉興の側室・由羅(ゆら)の方が、自らが産んだ子の久光(ひさみつ)を藩主に就任させるために暗躍しているからであり、斉彬を呪詛するために兵道家を雇っているとの噂が公然と鹿児島城下に流れ始めました。
この陰謀に憤りを覚えたのが、斉彬の藩主就任を熱望していた薩摩藩士・高崎五郎右衛門と近藤隆左衛門を中心とした一派です。高崎たちは、由羅の方と彼女を取り巻く反斉彬派の重臣が元凶であると考え、彼らを暗殺したうえで、斉興を隠居させ、斉彬を藩主に擁立しようと謀ったのです。
しかし、彼らの動きに過敏に反応した斉興は、烈火のごとく激怒し、高崎と近藤の二人に切腹を命じ、その他計画に関わった藩士たちに対し、切腹や遠島、謹慎といった重い処罰を下しました。
これがいわゆる「お由羅騒動」と呼ばれるお家騒動で、別名「嘉永朋党事件(かえいほうとうじけん)」や「高崎崩れ」、「近藤崩れ」とも呼ばれています。
このお由羅騒動は、若き日の西郷にも大きな影響を与えました。
西郷の父吉兵衛が用頼(ようだのみ)(注)を勤めていた日置島津家出身の赤山靱負(あかやまゆきえ)は、お由羅騒動に連座し、切腹を命じられてこの世を去りました。青年の頃から赤山の影響を受けて育った西郷は、父から赤山が切腹の際に着用していた血染めの肌着を受け取ると、終夜それを抱き、涙を流して赤山の志を継ぐことを決意したと伝えられています。(注:御用人のこと。身分の高い家柄の人の生活の世話をする人。鹿児島ではユタノンとも言う)
当時、西郷は下加冶屋町郷中の二才頭(にせがしら)(注)を務め、同じ郷中の吉井仁左衛門(後の幸輔、友実)や上之園郷中の伊地知竜右衛門(後の正治)、高麗町(これまち)郷中の有村俊斎(後の海江田信義)、そして高麗町から下加冶屋町に移住してきた、後年西郷の無二の盟友となる大久保正助(後の一蔵、利通)らと共に、朱子学の『近思録』を研究し、時事を談論する集団を作っていました。(注:二才とは薩摩地方で言う青年のことで、二才頭とは郷中教育における若手の長のこと。薩摩藩には、郷中教育と呼ばれる、町内ごとに青少年たちが組織を作り、自治的に年長の者が年下の者の教育を行う慣習があった)
後年、この若き二才たちの集団は「誠忠組(せいちゅうぐみ)」と呼ばれるグループに発展し、西郷はその首領格となり、藩政に大きな影響を与えるような集団へと成長していくのです。
【島津斉彬の襲封】
お由羅騒動により、斉彬を藩主に擁立しようとした一派は急激にその勢力を落とすことになりましたが、斉彬自身は藩主になることを決して諦めてはいませんでした。自らが得た知識や経験を藩政に生かし、大きな藩政改革を推進したい。諸外国の外圧が迫る未曾有の国難を迎えた日本のために自らの手腕を生かしたい。このような大きな経綸と志を持っていた斉彬は、藩主に就任するために一計を講じました。
斉彬は日頃から親しく付き合っていた幕府老中の阿部正弘、宇和島藩主・伊達宗城(だてむねなり)、斉彬の大叔父である福岡藩主・黒田斉溥(くろだなりひろ)の協力を得て、薩摩藩が密かに行っていた密貿易を幕府で問題にすることにより、斉興とその腹心であり、薩摩藩の財政責任者でもあった調所笑左衛門(ずしょしょうざえもん)を政治的に追い詰めようと画策しました。
当時の薩摩藩は、幕府から正式な許可を得て、琉球(現在の沖縄)を通じ、中国と貿易を行っていましたが、幕府から許可された金額を超える貿易を行なっており、不正に莫大な利益を上げていました。斉彬はそのことを問題にすることで、父の斉興と腹心の調所の責任問題に発展させようと考えたのです。斉彬にとって、自らの藩の秘密を公にさらすことは苦肉の策であり、諸刃の剣を使うようなものでしたが、藩主に就任するために敢えて苦渋の決断を下したのです。
そして、この斉彬の秘策は見事に的中しました。斉興の腹心であった調所はその責任を一身に負って服毒自殺して果て、また、その影響で、藩主斉興も隠居せざるを得なくなったのです。
こうして、ようやく嘉永四(一八五一)年二月二日、斉彬は島津家二十八代当主の薩摩藩第十一代藩主に就任しました。
そして早速斉彬は、薩摩藩を近代的な藩に変えるべく、様々な新規事業を藩内に興すことを実行に移したのです。
斉彬が推進した事業は、非常に多岐にわたります。
・蒸気船の製造
・汽車の研究
・製鉄のための溶鉱炉の設置
・大砲製造のための反射炉の設置
・小銃の製造
・ガラスの製造(薩摩切子(さつまきりこ)として今日でも有名です)
・ガス灯の設置
・紡績事業
・洋式製塩術の研究
・写真術の研究
・電信機の設置
・農作物の品種改良
池田俊彦『島津斉彬公伝』には、「今斉彬の施設経営せし事業の跡を検するに、凡そ西洋の文物にして採用すべきものは殆んど一も洩さざるを期したるもののようである」とあり、斉彬が当時の最先端技術を余すところなく、藩内に導入、推進したことが分かります。
また、オランダ人でありながら、幕府の創設した長崎海軍伝習所で教員を務めていたカッティンディーケは、伝習所の訓練生と共に薩摩を訪れていますが、その時の感想として、「鹿児島の備えは行き届いている。そうして時世に遥かに先んじている主君の統治下にあるのだ」(注)と述懐しており、斉彬の指揮のもと鹿児島が近代化に突き進んでいる様子もうかがい知れます。(注:カッティンディーケ、水田信利訳『長崎海軍伝習所の日々』東洋文庫)
また、同じく薩摩を訪れたオランダ軍医師のポンペは、「われわれ一行がここで見たすべてのものからしてつぎのことを予言できた。すなわち、この藩は国運隆盛の源泉となるものを増進し、また自力で技術研究に専念する明君の政治のもとにおいて、燦然たる彼岸に到達するであろうこと、(中略)、この藩はまもなく日本全国のうちでもっとも繁栄し、またもっとも強力な藩になることは間違いないということである」(注)と、当時の薩摩藩の繁栄ぶりを後年書き残しています。(注:沼田次郎、荒瀬進共訳『ポンペ日本滞在見聞記―日本における五年間―』)
現代において、斉彬が江戸時代随一の名君であり、開明的な君主であったと言われる所以は、この斉彬が興した様々な近代事業をもってしても分かるのではないでしょうか。
【西郷の江戸行き】
斉彬は新たな人材の発掘と育成にも力を注ぎ、藩士たちに向けて、藩政に対する意見書を求める布告を出しました。この斉彬が出した布告を見た西郷は、それ以来幾度となく意見書を書き、藩庁に提出したと伝えられています。
西郷が提出した意見書については、現物は残されておらず、その内容は定かではありませんが、藩の農政に関するものが主なものだったでしょう。推測するならば、西郷の意見書は、藩内の農民たちが重税に喘ぎ苦しみ、いかに困難な生活を強いられているのかを切実に訴えたものであったのではないでしょうか。これは郡奉行の迫田から学んだ、「国の根本をなすものは農民である」という、西郷の愛農思想に準拠するものだと言えます。
また、西郷は農政に関すること以外にも、先年のお由羅騒動で処罰された藩士たちが、未だ遠島や謹慎の処分を解かれていないことに不満を持ち、そのことも意見書の中に書いたと伝えられています。
通説では、これら西郷の意見書が斉彬の目に留まり、安政元(一八五四)年一月、斉彬が江戸に出府するにあたり、西郷はその供に加えられ、郡方書役助から中御小姓、定御供、江戸詰を命ぜられ、江戸に行くことになったと言われています。西郷、二十六歳の時のことでした。
斉彬の江戸出府に随行し、薩摩から江戸の薩摩藩邸に勤務することになった西郷は、藩から「庭方役(にわかたやく)」の役職を拝命しました。
庭方役と聞けば、植木職人のような印象を受けますが、西郷に期待されたのは、そのような仕事ではありません。当時、身分の低い藩士が、藩主や家老といった身分の高い人物に拝謁するには、随分面倒な手続きが必要でした。当時は封建制、つまり厳格な身分制度が存在する世の中であり、西郷のような下級藩士が、おいそれと身分の高い人々と簡単に話せるような時代ではなかったからです。西郷が庭方役を拝命したのは、西郷がこれまで度々提出した意見書を斉彬が読み、西郷のことを薩摩藩の将来を担う、頼もしい若者と感じたため、面倒な手続きを取らずに、自由に庭先などで会うことの出来る庭方役に任命したと伝えられています。
安政三(一八五六)年四月十二日、西郷は初めて藩主斉彬に拝謁した時のことを同志の大山正円(後の綱良)宛てた手紙の中で、「思っていた以上に感服しました」との感想を述べており、西郷が斉彬の英明さに感動を覚えた様子が分かります。
また、西郷は下級藩士である自分に対し、気軽に顔を合わせられる待遇とするなど、厚い配慮をかけてくれた斉彬に対し、涙が出んばかりに感激したのではないでしょうか。そして、「この人のためなら喜んで命を捧げよう」と誓ったことでしょう。
この日から、西郷は斉彬から国内の政治情勢や諸外国との関係、そして日本の政治的課題などを教え込まれ、人間的に大きく成長していくのです。
また、斉彬の厚い薫陶を受けた西郷は、当時天下に名を馳せていた水戸藩の藤田東湖(ふじたとうこ)や戸田蓬軒(とだほうけん)、越前福井藩の橋本左内(はしもとさない)といった志の高い人たちと交流を持つことになり、次第に西郷の名も諸藩士の間で知られるようになっていきました。
西郷は斉彬によって天下のことを知り、そして世に送り出されたと言えましょう。
戻る 次へ
メニューへ